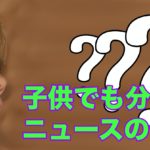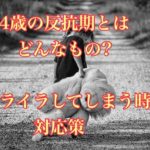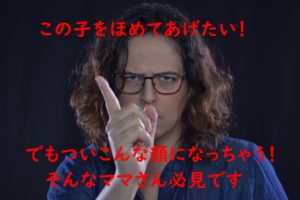皆さんは、子どもの教育をどのようにされていますか?
グローバル化や人工知能・AIなどの技術革新が急速に進み、予測困難なこれからの時代。
学校での学びの根幹である小学校教育指導要領は、2020年度から全面改訂されます。
これからの子どもたちに必要なこととは、どのようなことでしょうか?
私たちは親として、子どもにどう関わっていけば良いのでしょうか?
今回は、これからの教育の方向性と親がどのように子どもに接して行ったらいいかについて、小学生と幼児園児の2人の子どもを持つ私の体験談を交えながらご紹介していきます。
目次
学校教育は?これからの世の中は、どう変わる?

これからの子供たちの教育はどうなっていくのでしょうか?
2020年度から小学校はどう変わる?
小学校での学びも、知識を覚える教育から知識を活用する力を求める教育に変わりつつあります。
また、3、4年生から外国語活動や5、6年生で英語の教科化になります。
それから、2020年度よりプログラミング学習が始まります。
どのように変わるかについて、文部科学省HPの学習指導要領「生きる力」をご覧ください。
二つ目の動画『2020年度、子供の学びが進化!!よくわかる“新学習指導要領”』が、とても分かりやすくまとまっています。
AIに仕事をとられる時代?
今の子どもたちが大人になる頃には、半分くらいの職業が機械に代替される可能性があるとも言われています。
今の子どもたちは、現在存在しない職業につくだろうと言われています。
これからは、AI(人工知能・Artificial Intelligence)やロボットに任せた方が早く正確にできる仕事なら任せるようなことも増えてくると思います。
そんな風に言われると、これからどうなっちゃうんだろう…大丈夫かな…と心配になりますよね。
でも大丈夫です。
これからその方法をご紹介します!
良いところを伸ばす教育をしよう!
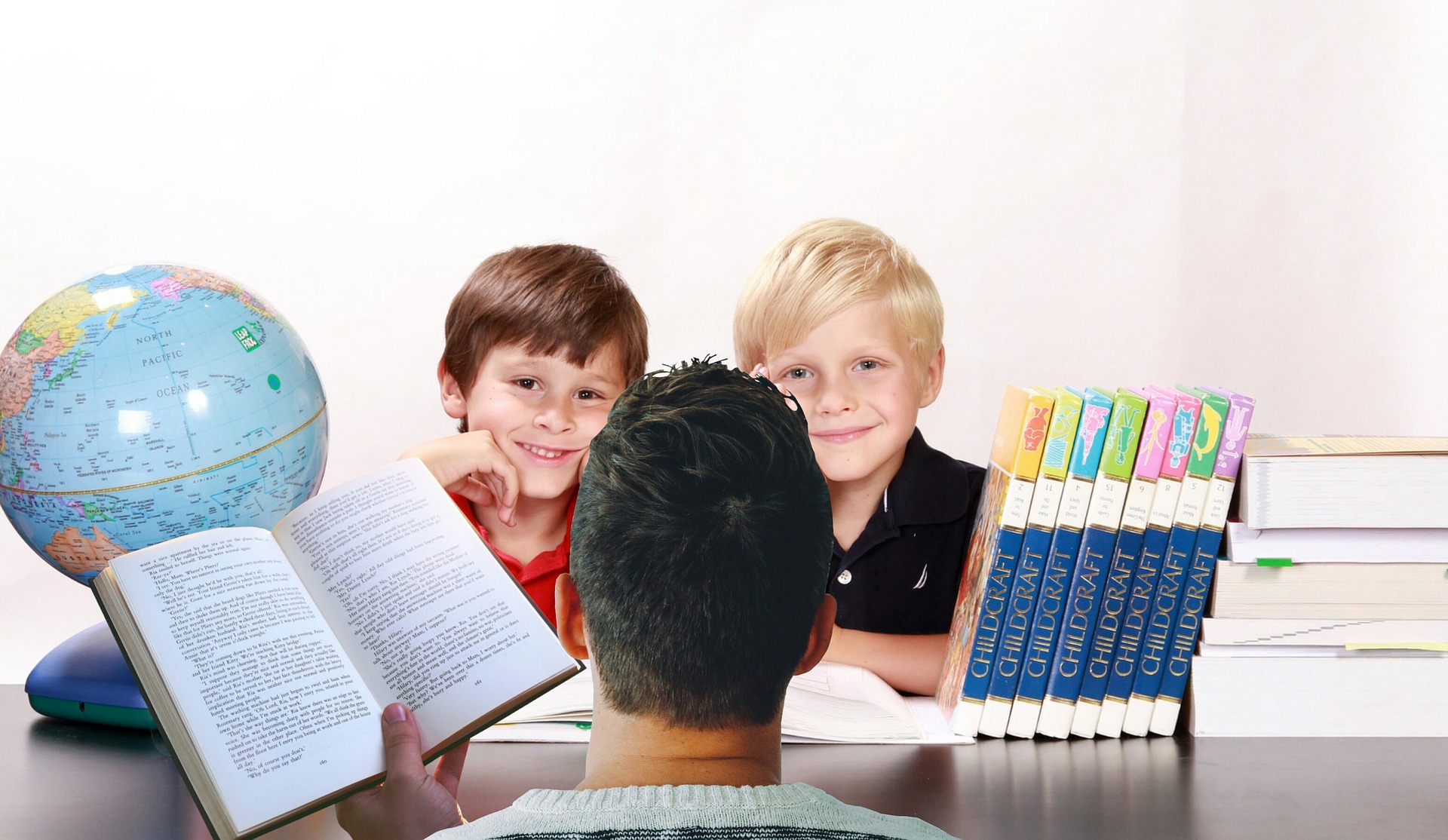
これからの子どもたちに必要な能力を考えるために、下記の文部科学省のホームページを参考にしてみました。
【21世紀を展望した我が国の教育の在り方について】
我々はこれからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を[生きる力]と称することとし、これらをバランスよくはぐくんでいくことが重要であると考えた。
引用:文部科学省
これからの子どもたちに必要なのは、自ら学び、自ら考え、主体的に行動することのできる能力です。

これらに対応できるような子どもにするために親としてすべきことは、親が全てを決めてレールを敷くのではなく、子ども目線で子どもにとって今必要なものは何かを常に考えてサポートすることだと思います。
子どもをよく観察し、子どもの良いところを伸ばす教育をしましょう。

幼児期に必要なこと

幼児期に必要なことは何でしょうか?
非認知能力を育てる
幼児期には、たくさん遊ぶ事が大切です。
お友達と一緒に遊びながら、時にはケンカをしたり、失敗したりしながら、自分で考えて新しい発想ができるようになるようにします。
これを非認知能力と言います。
「認知能力」 が、IQが高い、テストの点数がいいという、私たちが一般的にイメージする『勉強ができる』『頭がいい』ということなのに対し、「非認知能力」は、 学びに向かう姿勢(目標・意欲・粘り強さ) 学力で測れない能力(協調性・忍耐力・感情をコントロールする力)などを言います。
我が家の次男が通っている幼稚園では、この非認知能力を伸ばす教育をしています。
子どもが自分から興味を持ったことをとことん取り組ませるのです。
だから、園庭ではずーっとダンゴムシを追いかけている子、ずーっと砂場で穴を掘り続けている子などであふれています。
何かが出来た時、面白いことを発見できた時、子どもの笑顔はパッと輝きますよね。
それが集中力や自ら学び、自ら考える力になるのです。
その中から自分で本当に好きなことを見つけていくのです。
親はその手伝いをしてあげるだけです。
もし、ダンゴムシが好きなら図鑑を見せてあげましょう。
ダンゴムシはどんな形をしていますか?
足は何本ですか?
それが正しく描けるお子さんは、小学校に行っても漢字を正しく書けるようになるそうです。
まずは、お子さんの興味を持ったことをとことんさせてあげましょう。

家庭での関わり方は?

子どもが好きなことにどんどんのめり込むようになったら、応援してあげましょう。
好きなことを思い切りさせてあげよう
ぜひ、お子さんが夢中になって没頭していることをもっと深く知るために、調べる方法を教えてあげて下さい。
図書館へ連れて行ってあげても良いですし、もう少し大きくなったらインターネットでの調べ方も教えてあげるといいですね。
自分で調べる力をつけてあげましょう。
今までは子どもが『これは?どうして?』と聞いていたのに、いつの間にか大人よりも詳しく知っていて、大人のほうが『これは?どうして?』と聞くようになったらすごいですね。
人から押し付けられたものではなく、自分が好きなものだから、自分で調べたいしもっと知りたいと思うのだと思います。
この、自分からすすんで学ぶ力、考える力が生きる力となるのです。
これからは、子どもに好きなことを思い切りさせることが大切です。
私たち親は、それを充分にさせてあげる環境を作ってあげましょう。
好きなことの見つけ方
では、どのようにして好きなことを見つけていくのでしょうか?
我が家の例で見てみましょう。
長男は、1歳頃からショベルカーが大好きでした。
散歩に行く時は決まって工事現場に行きたがります。
ショベルカーを使った現場で飽きもせず、ずーっと見ていました。
毎日通うので、現場のおじさんと仲良しになった程です。
家に帰ると『工事現場で働くくるま』というDVDを見て過ごし、ショベルカーのおもちゃでずっと遊んでいました。
5歳頃になると、ショベルカーの絵を描くことに興味を持ち始め、毎日20枚くらい同じショベルカーの絵を描いていました。
そうして、絵を描くことに興味を持った長男はショベルカーだけでなく、新幹線や車などその時に描きたいと思ったものをどんどん描くようになります。
やがて、ゲームのキャラクターのイラストも描くようになり、今ではクラスのお友達に頼まれて描くようになりました。
このように、好きなことをどんどん伸ばしていって、いずれ将来役に立つことに繋がれば良いなと思っています。

本当は子どもをよく観察し、好きそうなことを見つけていくべきだと思いますが、何を好きになってくれるかは、やってみないと分かりませんよね。
我が家でも試行錯誤を繰り返してきました。
我が家では、長男が赤ちゃんだったころから英語に興味をもってもらおうとしたことがありました。
長男が1歳から4歳まで英語保育をしてくれる幼稚園に通わせていました。
そこではうちのように、英語に親しんでもらおうと通わせている家庭と、日本語がわからない外国の方の両方のお子さんがいました。
子どもたちは日本語も英語も片言でしたが、子ども同士では会話が成立しているようでした。
ただ、私には両方とも片言だった息子の言葉が理解できず、なかなか子どものことをわかってやれませんでした。
そのことが子どものストレスになり、幼稚園を嫌がるようになりました。
その頃、次男を出産し引越しましたので、家から近い幼稚園に転園しました。
そこは、伸び伸びと自由に遊ばせてくれる幼稚園でしたので、楽しく通う事ができました。
長男は、9歳になった今でも、英語は嫌いだし、苦手なんだそうです。
長男には悪いことをしたなと反省しています。
ところが次男は、英語とは無縁の環境で育てていたにも関わらず、テレビなどで英語に興味をもつようになったのです。
分からないものです。
現在は長男は絵を描くこと、次男は英語に夢中です。

興味を持ったことを伸ばしてあげるには?
子どもが興味を持ったものは、ゲームでも音楽でも何でもとことん応援してあげましょう。
子どもになぜ、それが好きなのか、どんなところに夢中になっているのかを日常の会話の中でどんどん聞いてみましょう。
親が子ども興味を持って聞いてやると、どんどん人に説明する力などがついてゆきます。
こうして論理的に考えるくせをつけてゆきます。
子どもと夢中になっていることについて楽しく会話するうちに、もしかしたら将来につながるヒントが見つかるかもしれませんよ。

AIに負けないために

長男が通う小学校では、主体的に行動する教育が始まっています。
例えば、担任の先生は号令をかけません。
並んで別の場所に移動しなければならない時、おしゃべりしていても先生は叱らず、子どもたちに今はどうすべきなのか、考えて行動するよう促します。
すると子どもたちは時間を気にして、『早く行こう』と声をかける子や遅れそうになっている子の手伝いをする子など、自分たちで考えて行動できるようになってきています。
そして、もう一つステップアップして、人間にしか出来ない能力を伸ばすということをイメージすることも、大事だと思います。
- お年寄りが立ちやすくなるよう椅子を工夫するなど、アイデアを生み出すこと。
- マニュアルにはない判断をするなど、柔軟な対応をすること。
- 相手の表情を見て話す内容や順序を考えること。
- お客さま一人一人に合わせてコミュニケーションをすること。
このように、思考力、感性、感情、アイデアなどを自分から考えて主体的に行動できる人は、これからもきっと役に立てる人間になれるに違いありません!!
そのために、これまでご紹介してきたことをぜひ試していただけたらと思います。
さいごに
これからの子どもたちに必要なことは、自ら学び、自ら考え、主体的に行動することだということが分かりました。
それはなにも、今すぐにそれらができる子を育てなければならないという意味ではありません。
出来なくても良いのです。
子どもは、いつの時代でも失敗を繰り返し、周りの友達や大人たちに助けてもらいながら成長してきました。
子どもは色んなことを経験しながら出来るようになってゆきます。
前述の『学習指導要領「生きる力」』でも、子供の成長のために、保護者だけでなく、地域の存在の重要性を指摘していました。
私たち親は、自分の子どもだけでなく、同じ地域に住む子どもにも手を差し伸べて、同じように育てていけると良いですね。
突然ですが
今、おしゃれできていますか?
私は子供が生まれてからというもの、まったくおしゃれができなくなりました。
子育てが忙しく毎日、同じ洋服を着て出社をしていました。そんなある日、職場の若い女の子に
「毎日同じ洋服で楽そうですね、でも私はそこまで女を捨てられません」
なんて言われる始末。子育てが忙しいからおしゃれなんて無理…そう思っていました。
しかし!
ものすごい簡単におしゃれができてしまう方法があったんです!
この方法ならお金も節約できるし、おしゃれも楽しめるし一石二鳥、いやそれ以上です。私はこの方法に出会ったおかげで毎日おしゃれを楽しんでいます。
職場でも「おしゃれですね!」って言われて最高に嬉しいです。