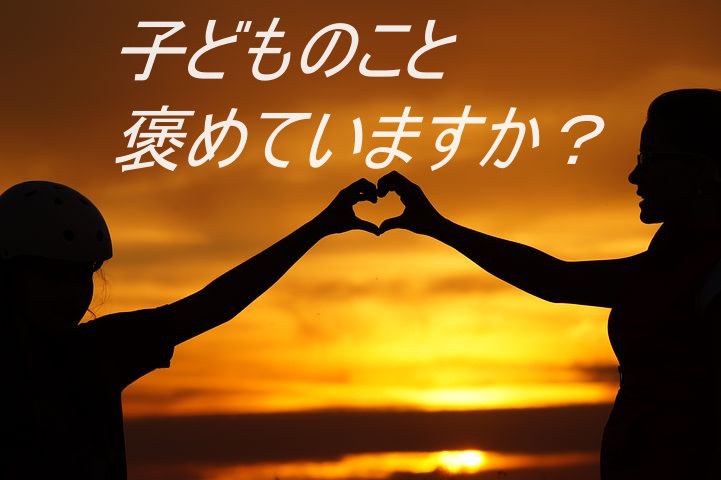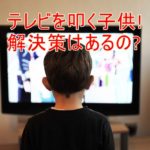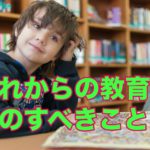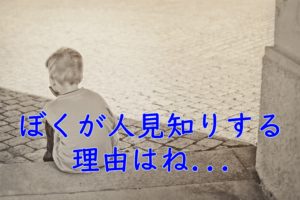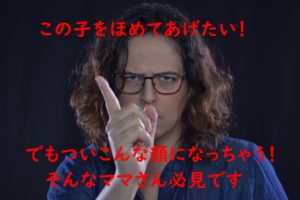突然ですが、皆さんは自分の子どものことを褒めていますか?全然褒めていない?褒めすぎてる?
家では、褒めることがあっても、人前ではなかなか褒めない、という方が多いのではないでしょうか?
特に、日本人は、謙遜するタイプの人間が多いように思います。
他人に褒められても、なかなか素直に「ありがとうございます」とは、言えないのではないでしょうか。
そんな世の中ですが、自分の子どもを褒める親について、どう思いますか?
褒めることには、メリットがある?褒めることのメリットや、褒める時の注意すべきことなどを紹介したいと思います。
目次
自分の子どもを褒める親 どう思う?

自分の子どもを褒めているママ友をどう思いますか?「すごいね」と素直に思えるでしょうか?
それとも、「人前で、自分の子どもを褒めるなんて…」と思うのでしょうか?
人の受け取り方は、様々ですから、相手がどう思うかは分かりません。
私は正直な所、両方思ってしまうかもしれません。
一度や二度だったら、素直に「すごいな」と思うかもしれません。
それが、毎度毎度となると、「ちょっと自分の子どもの事褒めすぎじゃない?」と思ってしまうと思います。

しかし、聞いている側としては、毎回子どもを褒められては、自慢話にしか聞こえてこないような気がします。
人前では、程々にがいいかもしれませんね。
また、そんな親御さんの話が自慢話に聞こえてくるようになったら、またその話がくるだろうと、流しておく程度がいいかもしれません。
自分がその話をきいて、我が子と比較することなく居られればいいのです。
変に対抗してしまうと妬んでいるなどと思われてしまう可能性があります。その方との付き合いが苦痛になるようなら距離を少し置きましょう。
そして同時に気を付けたいのが、人前で自分の子供を褒められた時に謙遜して「いえいえうちの子は全然ダメなんですよ」と否定してしまうことです。
子どもがそれを聞いていた場合、家では褒めてくれるのに、どうして外では??と混乱してしまうことがあるからです。
これでは、親と子供の信頼関係が崩れてしまいます。謙遜するのは日本人の礼儀というところかもしれませんが、上手に対応したいとこですよね。
|
「誰かに褒められ、謙遜しながらも子供を否定しない方法は?」 「ありがとうございます」と言って、その褒めてくださったお子様を褒めるというのはどうでしょうか? あまり知らない方のようでしたら、そんな点に気づいていてくれた方に「そんな点に気づいてくださってありがとうございます!」と返すのもいいかもしれませんね。 |
相手も褒められれば嫌な気がすることはないと思いますし、円滑な関係を保てそうですよね。
子どもを褒めて認めてあげる

皆さんは、どんな時に子どもを褒めていますか?お手伝いをしてくれた時、何かが上手にできたとき…。
褒める場面はたくさんありますよね
子どもは褒められると嬉しくて、褒められたことを何回もやろうとする、なんて事は、子育てあるあるではないでしょうか?
子どもにとって、”褒められる”というのは、本当に嬉しいものです。大人でも、褒められると認められたような気がして、嬉しいですよね。
この褒めるという行為、子どもにとっては、すごいパワーになるのです!
子どもは褒められるのが嬉しくてたまりません。
褒められたら、「もっと頑張ってみよう!」という意欲にも繋がるのです。
また、褒められることで、自信もつくのです。自分に自信を持つというのは、自己肯定感を高めるためにもとても大切なことなのです。
子どもの良いところを見つけて、どんどん褒めてあげましょう。
でも褒めるポイントを間違えないようにしたいですよね?
そのためには、どんな褒め方がいいのか知っておきたいところです。
自分の都合の良いときだけ子どもを褒めたり、誰かと比較してしまっていませんか?
そうならないための方法もお話していきたいと思います。
どうやって褒めるのがいいの?

”子どもを褒める!”といっても、具体的にはどうやって褒めてあげるのがいいのでしょうか?
私なりのポイントをいくつか挙げてみたいと思います。
少し大げさなぐらいがよい
褒める時は、「少しオーバーかな?」というくらいが、いいと思います。ママたちの演技力が試される所ですね⁽笑)
実際、私も褒める時はオーバーリアクションで褒めています。
例:子どもが苦手なものを食べられた時「えっ?!!これ、苦手なのに食べられたの?!!」と、かなり驚いた様子で言うのです。 |
文章では伝えきれないのが残念ですが…。
そうすると、子どもは得意げな顔をします。そして、もう一口、もう一口と、頑張って食べようとします。

そして、全部食べられたらまたここで、オーバーリアクション気味に褒める!
その時の子どもの顔といったら…。きっとみなさんも想像できるのではないでしょうか?
そう、すごいどや顔です!
でも、苦手なものを頑張って食べられたのですから、ここぞとばかりに褒めてあげてください!
褒める時は「できた事を言葉にして伝える!」
「凄いね」「上手だね」「偉いね」が誉め言葉の上位ではないでしょうか?
もちろん、それも良いと思います。
でも、もっといい褒め方があるのです。
それは、褒めてあげたい事を言葉にするということです。
例:上手に絵が描けた時「上手に描けたね」と言いがちですよね。 これをもっと具体的に言葉にするのです。 例えば、「色使いがきれいだね」、「上手に色が塗れているね」など、素敵だなと思うことを、子どもが分かりやすいように言葉にするのです。 |
そうすることで、どんな所を褒められたのか、子どもも分かりやすいのです。
また、それが、「今度はこんな色を使ってみよう」「もっときれいに塗ってみよう」という工夫する力や意欲にも繋がります。
時にはパパや兄弟などの前で褒める
人前で褒められるって大人でも嬉しいですよね。
子どもも一緒です。自分の頑張ったことがママだけでなく、家族にも認めてもらえたら嬉しいですし、自信にもなります。
人伝えに褒めるというのもいいですね。
例えば、パパが「さっき、苦手な物も全部食べられたってママから聞いたよ」と子どもに伝えるのです。これもよい方法だと思います。

人と比較しないで褒める
子どもができるようになるまでには、個人差があります。ですから、友達や兄弟と比べず、その子の頑張りを褒めてあげましょう!
比較されることで、自身を失くしてしまう可能性があります。
|
こんな言葉かけしていませんか?
「○○君はできるのに、あなたはダメね」 「○○君はできたから、あなたもできるよね!」
「なんであなたはこんなこともできないの? お姉ちゃんはちゃんとできたよ」 「お兄ちゃんは出来なかったのに、あなたはこんなに早くできてえらいね!」
|

- 子どもの話したいことは友達の話だったのに、自分を否定されては、友達のことを話せば自分のことを否定される。となってしまって話さなくなってしまう。
- お兄ちゃんができなかったけど自分ができたという優越感を持つようになる。
これは子供自身も人と比較してしまうようになってしまい、人より下回っていれば自信がもてなくなり、上回っていれば優越感を持つようになり、精神的に不安定になりがちになります。
無意識にやってしまうことで、自己肯定感を低くしてしまう可能性があるということです。
その子のその子の個々を褒めるということに意識をもっていきましょう。
先ほどから、何度か出てきている言葉ですが、そもそも、自己肯定感が低いことって、どんな影響があるのでしょうか?
褒める事で自己肯定感を高める?

自己肯定感ってなに?
「自己肯定感」という言葉をご存知ですか?
最近、メディアや育児本などでも取り上げられるようになり、ご存知の方もいると思います。
この自己肯定感というのは、分かりやすく言うと、自分を肯定する感情ということです。
つまり、自分の価値や存在意義を肯定できるということ。
自己肯定感が低いとどうなるの?
日本人は、世界的に見ても、自己肯定感が低いと言われています。
●自分はダメな人間だと考えてしまい、何かとネガティブに考えすぎる傾向がある。
●周囲からの評価を気にし過ぎてしまい、他人の顔色を伺う。
●承認欲求が強い。
●嫌われたくないため、言いたいことを言えない。など
このような傾向があるようです。

自分に自信が持てないため、他人の意見に流されてしまったり、自分が辛くても嫌だと言えない傾向があり、ストレスを抱え込みすぎてしまうように思います。
そんな私も、最近自分は自己肯定感が低いのではないだろうか、と感じることがあります。
- 相手に言われたことをいつまでも気にしたり
- 「自分はこう思う!」と思っていても、他の人の意見に左右されて、自分の意見を貫き通せなかったり…。
- 「他人は他人!自分は自分!それでいい!」となかなか思えないのです。

自己肯定感が高いとどうなるの?
それでは、自己肯定感が高い人には、どんな特徴があるのでしょうか?
●物事を前向きに解釈することができる。
●失敗することを恐れない。
●人と自分を比較することがない。
●物事を素直に受け入れられる。
●物事を肯定的に捉えられる。など。
自己肯定感が高い人でも、体調や環境によっていつでも前向きに考えられるというわけではないと思います。
時には、気持ちが沈んでしまうこともあるでしょう。ただ、もともと自己肯定感が高い人の方が、立ち直るまでの時間が短いのではないでしょうか?
褒めることで、自己肯定感が高まります。
「自分は素敵な人間なんだ」
「価値のある人間なんだ」と思えるようになります。
自己肯定感を高めることばかりを気にして、”叱るべき時に叱らない!”というのは、物事の良し悪しを学ぶ機会を逃してしまいます。褒める時は褒める、悪いことをしたら、きちんと叱る!というメリハリをつけましょう!
では、どんな風にそのメリハリをつけていけばいいのか?
メリハリをつけるってどういう事?

”子どもは褒めると伸びる!”なんて言葉聞いたことありますよね。
子どもも一人ひとり違いますから、褒めれば必ずしも伸びるとは言い切れません。
そして、褒めてばかりもあまり良いとは思いません。
なぜなら、子どもが褒められるために行動するようになる、というリスクもあるからです。
褒められるためにしている行動は、本当の自分ではありません。
|
【褒められないとやらない子になる?!】 保育士が片づけが出来たことを、むやみやたらにほめ過ぎていた「実例」です。 褒められすぎていたその子は、その保育士の前だけで急に良い行動、お利口な態度をするようになっていったそうです。 これがエスカレートしていくと、こんな行動になる可能性があります! 例えば)また「褒めてもらいたい」気持ちが優先して、褒められるために手段を選ばなくなってしまい、ゴミが落ちていないのに、わざとゴミを落として、大人が来たら自ら落とした、ゴミを拾い、ゴミ箱に捨てるなどの行為です。 |
これでは、本末転倒で意欲を高めるどころか、”褒められないならやらない”という風になってしまいます。
そうならないためには、どうしたらいいのでしょうか?
子どもの行動をよく観察することです。出来たことだけに焦点を当てずに、できるまでの過程を見るのです。
できるまで”一生懸命めげずに頑張った”・”失敗しても何度も挑戦した”など、できるまでの過程を見れば、褒める時のタイミングは分かってくると思います。
その過程も褒めてあげると、”努力を認める”ことにもなるので、子どもは、ちゃんと見てくれていたと、親の愛情を感じることもできます。
最後に
人前で自分の子どもを褒める親に、違和感を感じる方も多いと思います。私も、あまりにも頻繁だと、違和感を感じるでしょう。
人間関係を円滑にするには、褒めすぎるのは、いかがなものかと思います。
しかし、褒める事自体は、子どもにとって、とても良いことだと思います。
褒める時には、子どもの頑張りを認めるような褒め方を、叱る時には、子どもに分かりやすく明確に、を頭に入れながら、子ども達と向き合いたいものですね。
突然ですが
今、おしゃれできていますか?
私は子供が生まれてからというもの、まったくおしゃれができなくなりました。
子育てが忙しく毎日、同じ洋服を着て出社をしていました。そんなある日、職場の若い女の子に
「毎日同じ洋服で楽そうですね、でも私はそこまで女を捨てられません」
なんて言われる始末。子育てが忙しいからおしゃれなんて無理…そう思っていました。
しかし!
ものすごい簡単におしゃれができてしまう方法があったんです!
この方法ならお金も節約できるし、おしゃれも楽しめるし一石二鳥、いやそれ以上です。私はこの方法に出会ったおかげで毎日おしゃれを楽しんでいます。
職場でも「おしゃれですね!」って言われて最高に嬉しいです。