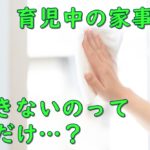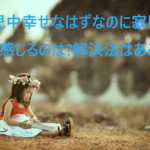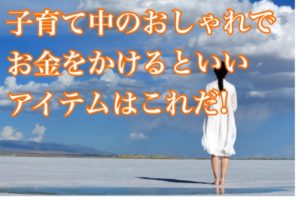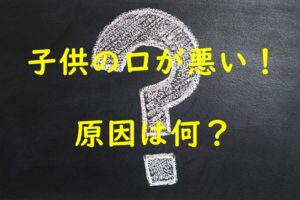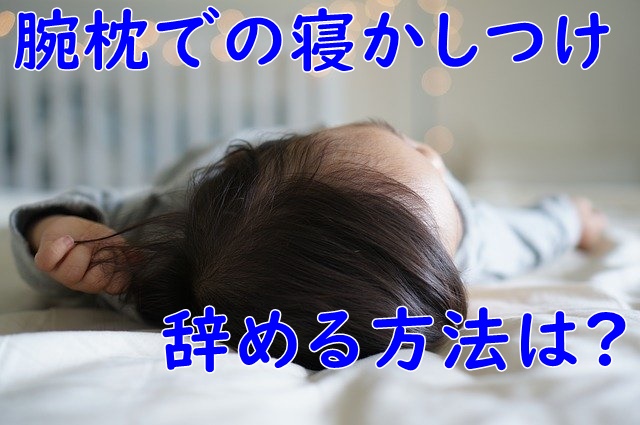お腹を痛めて産んだ我が子。我が子が生まれた時、どんな気持ちになりましたか?
きっと多くのママやパパは、幸せいっぱいの気持ちに包まれたのではないでしょうか。
その幸せを感じたのも束の間、慌ただしく子育てが始まります。忙しい毎日の中で、子育ての大変さばかりが目立ってしまってはいませんか?
幸せだなと感じる余裕もない!なんて方もいるかもしれません。
今日は、子育てを通して感じる幸せや、大変なこと、幸せに感じないのはなぜ?など、幸せについて書いていきたいと思います。
目次
子どもを育てる幸せとは?

子どもを育てる幸せをどんな時に、感じますか?
子どもの成長を実感した時
子どもは日々成長しています。特に生まれてからの1年間は、成長が著しいですよね。
初めて”はいはい”したり、立ったり、一歩踏み出せたり…。
その度に感動したのを、昨日の出来事のように思い出します。
8ヵ月の頃から、保育園に通い始めた長女。
入園してしばらく経った頃、周りのお友達が歩き始める中、全く歩き始めようとしない娘。
娘より月齢の低い子も歩き出し、成長が遅いのでは?と、不安になりました。
それからしばらく経ち、親戚の結婚式で海外に行った時のこと。
「ちょっと歩いてみようかな」と思ったのか、歩き始めようとした娘。
「これはチャンス!」と思い、歩ける場所を確保し、パパと交代しながら、娘が歩くのをお手伝いしました。
すると、一歩、また一歩と、歩き始めたのです。
「やったぁ!」
パパと一緒に大喜びをしたのを覚えています。
それからの娘は、歩くことに一生懸命。転んでも転んでも、頑張って歩こうとします。
保育園を長く休んでいたこともあり、娘が初めて歩くのをパパと一緒に見る事ができ、とても嬉しかったです。
心配していた私をよそに、歩くコツを覚えた娘は、すぐにテクテク歩けるようになりました。
休み明けに、保育園の先生やママ友も驚いたほど、上手に歩けるようになっていたのです。
子どもの笑顔を見た時
子どもの笑顔は本当に可愛いですよね。
笑顔を見ると、一日の疲れも吹っ飛ぶ!なんてことも。
そんな私を見た3歳の次女が、満面の笑みで私を覗き込んできました。
その笑顔を見て、ついつられて笑ってしまった私。疲れが一気に吹っ飛びました。すると、娘も嬉しそうににっこり。
「笑って欲しくて、こんなことしたのかな?」と嬉しく思った出来事でした。
何気ない日常を過ごしている時

一緒に買い物をしている時や、お風呂に入っている時、布団の中に入ってお話をしている時など。
子育てをしていると、毎日バタバタと過ぎていき、1週間があっという間。
でも、特別なことがなくても、笑顔でいられたら、それだけでも、幸せなことだと思います。
先日、娘たちとお風呂に入っていた時のこと。
保育園で覚えてきた歌を歌い始めた3歳の娘。
「ゆ~きやこんこ、あられやこんこ~」
冬の定番曲です。
上手に覚えてきたなと思っていたら、
「ね~こは、こたつではいりまる~」
「ん?」
きっと、こたつに入ると、丸くなるが混ざったのでしょう。
大爆笑です。そして、娘も大爆笑。
とても幸せな気分になりました。
そんな日常に溢れている幸せを見落としたくないものですね。
子どもの寝顔を見た時
起きている時は、「ママ~」の連続でクタクタになったり、言うことを聞かなくて、イライラすることも数知れず…。
寝る直前まで、騒がしいなんてこともありますよね。
でも、起きている時の騒がしさが嘘のように、スヤスヤと寝ている姿を見ると、つい微笑んでしまいます。
”子どもの寝顔は天使”なんてよくいいますよね。まさにその通りだなと、思います。
先日、「幸せだな~」なんて思いながら、長女の寝顔を見ていました。
すると、突然!
「えっ?何?これは夢なの?」
と大きな寝言。
「どんな夢を見ているんだろう」と微笑ましく思ったエピソードでした。
そんな娘が生まれたばかりの頃は、乳幼児突然死症候群(SIDS)が心配で、夜中に何度も呼吸の確認をしていました。
時々、呼吸が聞き取れず、ドキッ!としたこともありましたが、お腹が動いているのを見て、ほっとしたのを覚えています。
〇乳幼児突然死症候群とは?
乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)
とは、何の予兆や既往歴もない乳幼児が、睡眠中に突然死に至る、原因不明の病気です。
SIDSの予防策は確率していませんが、下記の3つのポイントを守ることで、SIDSの発生率が低くなるといわれています。
- 1歳になるまでは、仰向けに寝かせるようにしましょう。
→うつ伏せ、仰向けのどちらの状態でも、発生しますが、うつ伏せに寝かせた時の方が、発生率が高いそうです。 - できるだけ母乳で育てましょう
→母乳で育てられている赤ちゃんの方が、発生率が低いそうです。 - たばこをやめましょう
→SIDS発生の大きな危険因子と言われています。妊娠中の喫煙は、お腹の中の赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも悪影響を及ぼします。
他にも、睡眠中に亡くなったというケースがあるようです。
例えば、添い寝の状態で、授乳をしてそのまま眠ってしまい、お母さんが赤ちゃんを窒息させてしまったというケース。
他にも、スマホなどの充電器を枕元に置いておいたら、それが、赤ちゃんの首に巻き付いてしまい、窒息してしまったなど。

子育ては楽しいことばかりではありません。もちろん大変なこともたくさんありますよね。
子育てで大変な事って?

子どもは可愛くても、毎日の子育てはやっぱり大変。
子育てで大変なことは一体どんなことなんでしょうか?
自分の思い通りに物事が進まない
子どもがいると、なかなか自分の予定通りにはいかないもの。頭では分かっているものの、心に余裕がないとつい、イライラしてしまいますよね。

- 前もって、予定を伝えておく
→子どもも見通しを立てることができるので、意外とすんなり、話を聞いて、動いてくれます。 - 最悪な場合を想定する
→例えば、自分でお茶をコップに入れたいと子どもが言ったら、溢すかもしれないと思う。そうすれば、実際に溢しても、仕方ないかと思えるし、溢さずにできたら、子どもと一緒に喜びを共有できます。※子どもを信じていないというわけでは、ありません。
「溢すでしょ」、「やっぱり溢したじゃない」など
子どもの自尊心を傷つけるような発言は止め
ましょう。 - 子どもが何か集中している間にやるべき事を済ませる
→子どもが何かに集中している時は、チャンスです!
集中を妨げないように、できることを済ましてしまい
ましょう! - 子どもの片付けがなかなか終わらない時
→競争にすると、あっという間に終わります。
例えば、「ママの食器洗いとどっちが早いかな?」というと、物凄いスピードで片付け始めます。怒られてやるより、何倍も早く、楽しくできるので、お勧めです。
悩みが尽きない
子育ての悩みって、無くならないですよね。年齢毎に色々な悩みが出てくるし、一つ解決したなと思ったら、また別の悩みが出てきて…。
子育ては、結果がすぐに出るものではないので、これでよかった!と思えるのは何年も経ってから…。

そんな子育ての悩みとどうやって向き合っていくべきなのでしょうか?
- 誰でも子育ての悩みはある
→子育ての悩みがあるというのは、子どものことを一生
懸命考えている証拠だと、自分を褒めましょう。
- 悩みを共有する
→一人で悩んでいても何も変わりません。パパや信頼できる友達に相談してみましょう。悩みを共有できるだけるだけでも、心が軽くなります。また、自分とは違う意見や考えを聞くことで、プラスになることもあると思います。 - インターネットや育児書ばかりに頼り過ぎない
→参考にする程度であれば、問題ありません。でも、あまりにも、頼り過ぎてしまうと、その通りにならない子どもにイライラしたり、不安になったりします。 - 自分の子どもをよく観察する
→自分の子どもを観察することってなかなか無いですよね。でも、じっくりと観察してみると、普段は気づけないような事にも気づくことができます。それが、意外と悩みを解決してくれるかもしれません。
お金がかかる
食費やおむつ代、洋服代に学費など、子育てにはお金がかかります。
進路によって大きく変わりますが、0歳から大学を卒業するまでに、3000万かかると言われていますよね。
医療費の負担や子ども手当などがあるものの、それでもやっぱり足りないですよね。

- 児童手当など支給される手当を貯めておく
→児童手当は、3歳未満の子どもは一人につき月額15,000円。3歳から小学生までは、10,000円(第二子まで)。第三子以降は15,000円。中学生になると、10,000円が支給されます。
※中学までで受給できる金額は198万となります。 - 保険を活用する
→学資保険や終身保険を活用する。学資保険の利率の良い物を探したり、終身保険で学資保険の変わりになるものを探し、コツコツ貯めていくという方法があります。 - 家計を見直し、削れる部分は節約する
→例えば、子ども服。子どもの成長は早いもの。洋服もすぐにサイズアウトしてしまうこともありますよね。そんな時はアウトレットやリサイクルショップなどで購入するのも一つです。
特に、入学時には、まとまった費用が必要になるもの。その時に慌てない様に、計画的に貯蓄していきたいですね。
子育ては、責任ある大仕事!そんな子育てに”幸せを感じられない”という方もいるのではないでしょうか?
子育てに幸せを感じられない?

子どもがいるママやパパ、みんなが幸せを感じているとは限りません。
生まれる前と、生まれた後の生活が激変し、そのギャップに疲れてしまうという人もいるでしょう。
でもだからと言って、幸せを感じられない自分を責めてはいけません。
特に、出産後はかなりの体力を消耗しています。そんな中、新生児のお世話は本当に大変ですよね。
産後の身体は心身ともに疲れ切っています。

初めての育児に緊張や不安がたくさん。主人は帰りが遅かったので、子どもと二人の時間がとても長く感じていました。
そんなある日、夜に泣き出した娘。お腹が空いているわけでもないし、おむつも変えたばかり。
抱っこの仕方を変えたり、抱っこしながら部屋の中を動いたり…。色んなことを試しても、全く泣き止む様子がありませんでした。
当時は、アパート暮らしだったので、「静かにさせなきゃ」という気持ちもありました。
そんな私の気持ちをよそに、泣き続ける娘…。
どうしたら良いのか分からなくなり、ついに一緒に泣き出してしまいました。
主人が帰ってきて、選手交代!しばらくしたら、泣き疲れたのか、やっと、眠ってくれました。
結局何が原因かは分かりませんでしたが、そんな事が何回かありました。
その度に、娘の泣いている意味が理解できない自分の不甲斐なさを感じたり、どうしたらいいのか分からないという不安を感じたり…。
幸せだと感じる時間の方が少なかったように思います。
それから、子どもが成長していき、おしゃべりができるようになると、会話することが楽しくなり、孤独感を感じることも少なくなりました。
また、子どもがある程度自分の事が一人でできるようになると、心にも余裕ができるようになりました。
幸せだと感じるためには?

幸せを感じるのは、人それぞれですが、幸せを感じる時というのは、余裕がある時なのではないでしょうか?
自分に余裕が持てるようにするためには、どうしたらよいのでしょう。私なりの方法をお伝えします。
例え5分でも10分でも、1人だけの時間があるのとないのとでは、全く違います。
〇人と話す時間を作る
”一日中子どもと二人っきり”というのは、孤独を感じやすいもの。友達と話す時間が作れないという場合には、スーパーなどに買い物にいくだけでもGOOD!店員さんとちょっとしたやり取りをするだけでも、気分が違います。
また、赤ちゃんを連れていると、話しかけてくれる人もいます。「かわいいわね」なんて言ってもらえると、嬉しいですよね。
〇周りの人に助けてもらう
疲れていても、「皆やっていることだし」と、ついつい頑張っていませんか?
疲れた時には、きちんと身体を休めることも、大事なことです。育児には、体力と気力が必要です。子どものためにも、休める時には、しっかり休みましょう。
幸せを感じられないことは、悪いことではありません。きっと、身体が疲れていたり、心に余裕がないからではないでしょうか?
自分を大切にすることも、幸せを感じるためには必要なことだと私は思います。
親なら誰しもが子どもの幸せを願っているもの。どうしたら、子どもは幸せになれるのでしょうか?
子どもの幸せを考えよう!

幸福度の高い子どもに育てるためには、親としてどんな事に気を付けたら良いのでしょうか?
子どもをコントロールしないこと
ここでいうコントロールとは、心理的なコントロールのことです。つまり、子どもの心理に干渉して、それをコントロールするということ。
例えば、子どもが決めた事に口出ししたり、親の考えを押し付けようとしたりすることです。

子どもを一人の人間として関わる
親と子どもは、別人格の人間ですから、考え方が違って当然です。
子どもの意見が自分と違っていたとしても、その意見を尊重し、認めてあげることが大切です。
ここで、気を付けたいのは、子どもが間違っていることを言っている時には、きちんと注意するということ。
そこでも、子どもの意見を否定するのではなく、気持ちを受け入れつつも、いけない理由を簡潔に伝えましょう。
相手を尊重することは、思いやりを感じさせる効果的な方法の一つです。
安心できる家
家でも外でも”いい子”は、危険です。
親にとっては、育てやすいと思っても、子どもは頑張り過ぎている可能性があります。
子どもなりに、家の外では一生懸命頑張っているのです。その上、家でもいい子だったら、子どもは気が休まる時がありません。
家庭は、外で頑張っている子どもが、ガス抜きできるような場所であるべきなのです。
甘えると甘やかすの区別を
「抱っこして」と子どもが言ってくることありますよね。これは、甘えている証拠です。親に受け入れられているという安心感を持ち、素の自分をさらけ出せている証拠です。
そんな時は、可能な限り甘えさせてあげましょう。十分に甘えさせてもらった子どもは、しっかりと自立できるようになります。
ここで、気を付けたいのは、「甘やかす」とは意味が違うということです。
例えば、買い物中、子どもが欲しいものを見つけ、「欲しい」と駄々をこねたとします。
そんな時、駄々をこねるからという理由で仕方なく買ってあげるという事です。
甘やかすというのは、一時的にはいいかもしれませんが、継続的にしていると、自分勝手でわがままな子どもになってしまいます。
幸せを見落としていませんか?

SNSが普及している時代。スマホが手放せないという方も多いと思います。
静かにさせたいからと、子どもにもスマホを与えて、スマホに子守りをさせていませんか?

「スマホに子守りをさせないで!」という言葉を聞いたことがありますか?
視力の発達の妨げになったり、親子同士の触れ合う機会が減ったりと、早くからスマホを子どもに与えるのは、よくありません。
特に幼児期は、まだまだ発達過程の段階。この時期は、人と触れ合った遊びや、身体を使った遊び、季節を感じるような実体験が大切です。
そんな大事な時期に、スマホばかりを与えては、子どもの成長を親が自ら止めているような物です。
また、大人もついつい、スマホに気を取られてしまうことありますよね。調べものをしたり、友達との連絡を取り合ったり…。

実際に、シンガポールのある小学生の作文が元になっているそうです。
その少年が学校から「親のことについて作文を書く」という宿題が出た時に書いたのが、「スマホになりたい」というタイトルの作文だったのだとか。
「ママがスマホばかり見てるから、僕はスマホになりたい」と。
「もっと僕のことをよく見て!」という切ないメッセージだったのでしょう。
スマホに気を取られて、子どもを見ていないと、安全面でも危険な場合もあります。
それだけでなく、日々成長している姿を見逃してしまう可能性もあるのです。
スマホが悪いわけではありません。また、「スマホを使うな」というわけでもありません。
しかし、スマホに費やしている時間を、可能な限り少しでも、子どもとの時間に変えられたら、親子の関係は、より親密になるのではないでしょうか。
親子の関係がしっかりとしていれば、子どもはきっと安心して自立していけるでしょう。
そして、それが、子どもの幸せへと繋がっていくのではないかと、私は思います。
最後に
1人の人間を育てるというのは、大仕事です。
親としての責任もありますし、悩みも絶えません。
自分のやりたいことを我慢したり、犠牲にしなければいけないことも増えていきます。
もしかしたら、喜びや幸せを感じるよりも、大変だと感じる事の方が多いのかもしれません。
しかし、だからこそ、ふとした瞬間に感じる幸せが、大きな喜びになると思います。
また、その喜びが、自分の生きるエネルギーにもなるのではないでしょうか。
突然ですが
今、おしゃれできていますか?
私は子供が生まれてからというもの、まったくおしゃれができなくなりました。
子育てが忙しく毎日、同じ洋服を着て出社をしていました。そんなある日、職場の若い女の子に
「毎日同じ洋服で楽そうですね、でも私はそこまで女を捨てられません」
なんて言われる始末。子育てが忙しいからおしゃれなんて無理…そう思っていました。
しかし!
ものすごい簡単におしゃれができてしまう方法があったんです!
この方法ならお金も節約できるし、おしゃれも楽しめるし一石二鳥、いやそれ以上です。私はこの方法に出会ったおかげで毎日おしゃれを楽しんでいます。
職場でも「おしゃれですね!」って言われて最高に嬉しいです。