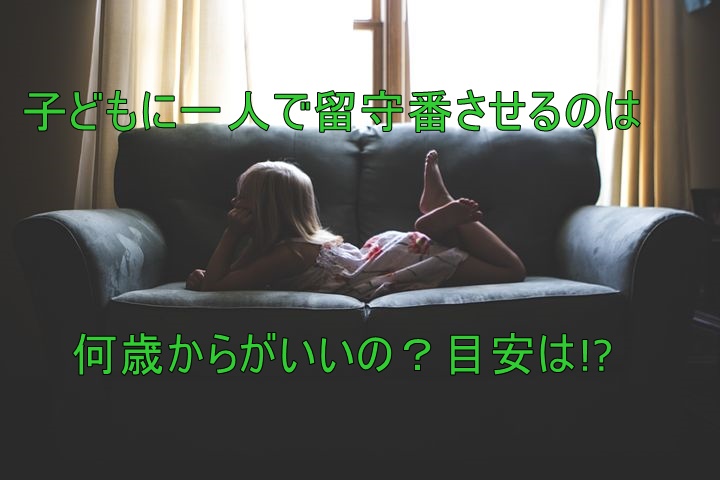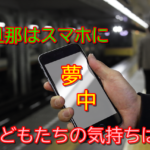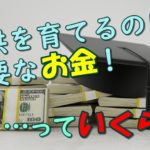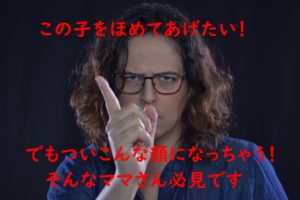私の家の近くには小学校があり、お友達同士で仲良く帰っている子もいれば、一人で歩いて帰っている小学校低学年と思われる子供とすれ違うこともあります。
特に冬など、暗くなるのが早い季節は、小学生とはいえまだ幼い子供が一人で大丈夫かな?
と心配になったりすることも…。
というのも、私は当時で言う「鍵っ子」でした。
小学校低学年ではなかったものの、小学校が終わったら、自分で家の鍵を開け、母が仕事から帰ってくるまで、一人で家で過ごしていました。
週に何回かは一人で習い事へ行って帰ってくる日もありました。
共働き家庭の増加や、必ずしも学童保育に希望者全員が入れないことを考えると、私の幼少期の時代よりも、もっと早い年齢から一人で留守番をしている子どもは多いのかと思います。
そこで、今回は子供が留守番を始める年齢や目安について紹介していきたいと思います。
お留守番は何歳からできるの?

例えば、日中にちょっとそこのコンビニまでお母さんが一人で買い物に行く程度など、少しの間、子どもが一人でお留守番できるのは一般的に小学校1〜3年生ぐらいからとされています。
しかし、その子どもの性格などによって、一人ひとり判断基準は違いますし、どのくらいの時間一人で留守番をするのかにもよります。
いきなり一人で留守番させるのは子供の安全面からも心配なので、少しづつ練習をしてから、長時間の留守番に挑戦すると安心です。
共働きのご家庭の場合、子供が保育園に通っている間は、家族がお迎えに行くまで、園の中では先生の監視下で過ごしていたでしょう。
そんな環境が小学校へ入学すると、ガラッと変わります。まとまった時間1人でお留守番するためには、事前の準備が必要不可欠です。

小学生になってからは、小学校の学童保育を利用することもできますが、実は、保育園より預かってくれる時間が短いことがあります。
学童保育
小学校の空き教室や公民館などを利用し、共働きやひとり親の家庭などの児童を預かる仕組み。指導員のもとで宿題をしたり、遊んだりしながら放課後を過ごす。公設や民設など地域により様々な運営形態がある。 全国学童保育連絡協議会(東京)によると、全国で2万2096クラス(昨年5月1日現在)あり、93万3535人の児童が利用。現在、児童福祉法では対象を「おおむね10歳未満」と規定。小1~3年のみの利用が多いが、今年4月に対象を「小学生」とする改正法が施行されるため、施設や指導員の確保が急務となっている。
(2015-02-19 朝日新聞 朝刊 和歌山3・1地方)
また、学童保育は小学校低学年の子供が優先で入れるという自治体も多く、このため実際には小学3、4年生から一人で数時間お留守番を始めたという子も多いようです。
約束事を守れるようになってから留守番を始める
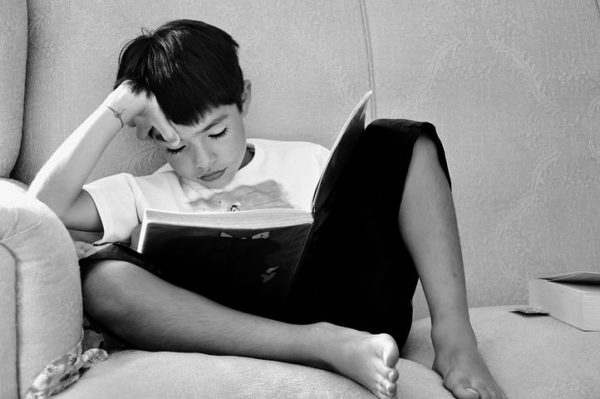
子供の性格や家庭の方針によっても変わってきますが、子供が安全にお留守番するためには、子供にいくつかの約束事を理解して、守ってもらう必要があります。
ですので、まずはお母さんとの「約束を守れる」ということが、とても大切な基準になります。
子供が留守番するときの約束事
●【インターホンに出ない】
基本的に留守番中は知らない人が来ても、インターホンに応えず絶対に家の扉を開けない。
|
インターホン越しに「お家の人はいますか?」などと聞かれても困るため |
基本的に一人のお留守番の時はインターホンに出ない方が安心です。
【親の不在時にお友達が来るケース】
親の目の届かないところで何かトラブルが起こる心配もあるため、
親の不在時はお友達を家にあげないようにするルールにしているご家庭も多いようです。
●【家の電話は留守電にしておく】
家の電話は留守電の設定にして置き、基本的に出ない。
もし、留守電に替わってお母さんや家族からだと分かったら出る…などの対策を考えて、知らない人との通話をすることは避けましょう。
子供が留守中の家庭を狙う犯罪も実際にあり、不安要素を取り除くためにも、念には念を押しておくと良いです。
●【家族に連絡なしに外に出ない】
習い事などに行く場合を除いて、お母さん(お父さんや家族)が把握していない場所に勝手に出かけない。
出かける場合は、必ず事前にお母さんに連絡する。
●【火は使わない】
子供が一人で火を使うのは危ないので、コンロは使わず、電子レンジのみ使用可とする。
●【何かあったらまず、お母さん(お父さんや家族)に連絡する】
最近ですと、子供にスマホを持たせているご家庭も多いかと思います。
具合が悪くなった、怪我をしたなどの緊急の場合は、すぐにお母さんの携帯に連絡を入れるようにしましょう。
|
スマホがない場合でも、目立つところに貼っておくといざというときに役立ちます。
「職場に電話をかけるとき」 何と言って電話をかけてよいか子供が困ることがあります。 そんな時のために、電話口で何といえばいいか一覧に一緒に書き留めておくと緊急時に安心です。 |
何か心配なことがあれば、ためらわずにお母さんに連絡するように約束しましょう
- インターホンに出ない
- 家の電話は留守電にしておく
- 家族に連絡なしに外に出ない
- 火は使わない
- 何かあったらまず、お母さん(お父さんや家族)に連絡する
以上のことが守れるようであれば、5分~10分の短時間から留守番の練習をしてみてもいいかもしれません。
留守番に慣れた頃のさらに重要な約束事
子供が短時間の留守番に慣れてきて、学校から一人で帰ってきて留守番をする場合は
さらに以下の約束事が重要になってきます。
●【家の鍵は絶対になくさない】
まず、家の鍵をなくしたら家に入れないので大問題です。鍵の取り扱いには十分気を付けさせましょう。
鍵をなくしてしまうと、安全面を考えて、鍵ごと交換する必要が出てきてしまいます。
●【家に入る時は周囲をよく確認する】
これは女性の一人暮らしなどでも言われることですが
鍵を開けた時に、不審者が一緒に家へ入って来るようなことがあっては危険です。
必ず、一度周囲を確認してから家に入るようにさせましょう。
●【帰宅したらすぐに施錠する】
帰宅後は必ず家の鍵をかける。
大人でもうっかり忘れてしまうことがありますが、子供の安全を確保するためにとても大事なことです。
- 家の鍵は絶対になくさない
- 家に入る時は周囲をよく確認する
- 帰宅したらすぐに施錠する
留守番に慣れてくると、忘れてしまいがちな項目を挙げています。
安心して、家での留守番を任せられるように1つ1つ注意していきたいですね。
まとめ
保育園の時は、仕事が終わる時間まで子供を預かってくれたけど、小学生になってからどうしよう、と考えているご家庭も多いかと思います。
子供が一人で留守番しているとなると親御さんも心配が尽きないですよね。
子供が一人で留守番を始める目安は、その子によって違ってくるので何歳からと一律に線引きするのは難しいですが、親御さんとの約束事を守れるかどうかが一つの基準となります。
約束事が守れるようになってきたと思ったら
いきなり長時間の留守番ではなく
普段の土日などに、短時間から練習を始めて
留守番の間に何か困ったことはなかったか、聞いたりしながら練習していくと
子供にとっても、親御さんにとっても安心かもしれません。
子供にとっても私たちママにとっても、少しでも安全に安心して留守番させられるようにしたいですね。
突然ですが
今、おしゃれできていますか?
私は子供が生まれてからというもの、まったくおしゃれができなくなりました。
子育てが忙しく毎日、同じ洋服を着て出社をしていました。そんなある日、職場の若い女の子に
「毎日同じ洋服で楽そうですね、でも私はそこまで女を捨てられません」
なんて言われる始末。子育てが忙しいからおしゃれなんて無理…そう思っていました。
しかし!
ものすごい簡単におしゃれができてしまう方法があったんです!
この方法ならお金も節約できるし、おしゃれも楽しめるし一石二鳥、いやそれ以上です。私はこの方法に出会ったおかげで毎日おしゃれを楽しんでいます。
職場でも「おしゃれですね!」って言われて最高に嬉しいです。