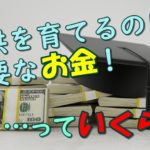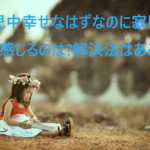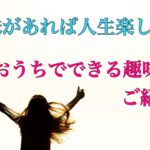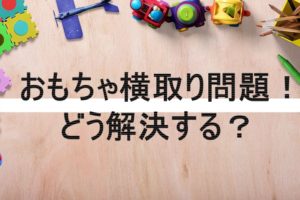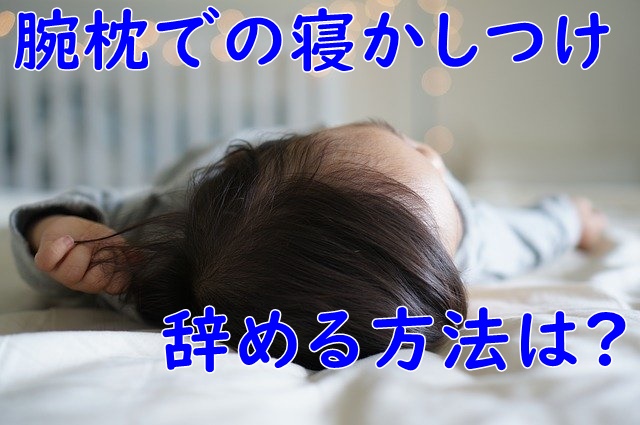一人目の子供と二人目の子供とで、育児の仕方や考えが変わってくるのは当たり前のことですよね。
私自身、2人の娘を絶賛子育て中ですが、一人目ではうまくできたけど、二人目では同じことができなかった…なんてことがたくさんあります。
一人目育児が大変だけど、二人目も欲しい…
でもうまく乗り越えられるか不安…
そう感じている方に、私が子育てを通して感じた、一人目と二人目の子育ての違いや、考え方の変化などを書いていきたいと思います。
私の体験談をもとに書いているので、個人差があるということを念頭に置きながら、参考にしてみてくださいね。
目次
一人目の子供と二人目の子供の大変さの違い
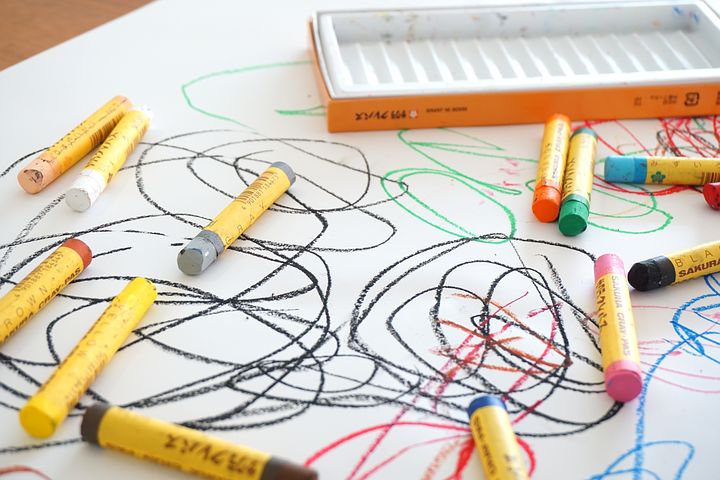
もちろん、その子供にもよって変わってきますが、一人目と二人目とでは、大変さが違ってくるもの。
では、大変さの違いにはどんなことがあるのでしょうか?
一人目育児の大変さ
一人目の子供は、分からないことが多いので不安も大変さもたくさん感じますよね。
~出産~
初めて経験することは、誰だって緊張するし、不安もあります。
まさに、出産もその通りではないでしょうか。
このように、一人目の出産の大変さは”経験したことのないことを初めて経験する”ということといえるでしょう。
つまり、”何も知らないからこその怖さ”とも言えますね。
「鼻からスイカが出る痛さ」ということを聞いていたので、相当痛いんだろうな…という覚悟はしていました。
予定日よりも一週間近く早く、破水してしまったため通院してすぐに入院になりました。
そこから地獄のような痛みがやってきました。
ついに、始まった…。
そして、痛みの間隔が段々短くなってきました。
助産師さんが、時々様子を見に来てくれるのですが、その度に、「まだまだねぇ」と分娩室に移動はできず…。
数十分後、何かが出てきそうな感じが。
でも、さっき「まだまだね」と言われたし…と我慢していました。
しかし、この感覚はいよいよ「赤ちゃんが出てくるのでは?」と思い、助産師さんに声をかけることにしました。
すると、「あらっ!出てきてるわ!急いで分娩室へ」と、やっと分娩に移動することができました。
それからは、早く楽になりたいという思いで、必死だったことしか覚えていません。
分娩室に入ると、予想以上に早く出てきてくれて、ほっとしたのも束の間。
その後も、しばらく痛みは続きました。
実際に経験してみないと分からないものだな…と改めて思いました。
そして、痛みも落ち着いた頃になってやっと、「無事に生まれてきてくれてよかった」と思えたのでした。
~子供が生まれてから~
出産したのもつかの間、子供が生まれてからがまた大変。特に初めての授乳には、とても苦戦しました。
ママも赤ちゃんも初めて同士。うまく授乳できるまで、時間がかかりました。
そして、おむつ交換も初めて。モタモタしている間にまたおしっこが出てしまう…なんてこともよくありました。
一人目育児あるあるかもしれませんね。
沐浴も、人形を使って練習したことはあったものの、実際にやってみるとこれまた大変!
「練習は一体何だったんだ?」と思うぐらい。
「耳に水が入らない様にしなきゃ」とか、「早く終わらせなきゃ!」と、気持ちは焦るばかりで、手際よくできない。

とにかく、やること全てが初めてなので、一つ一つに時間がかかり、本当に大変でした。
また、少しでも異変があると何か病気なんじゃないかと不安になり、スマホで検索なんてこともよくありました。

また、生後一か月までは、お出かけもほとんどできないので、”赤ちゃんと自分だけの時間が長い”ということで、孤独感を感じたり、ナーバスになりやすいものですよね。

では、二人目の子供の大変さはなんでしょうか?
二人目育児の大変さ
二人目は、一人目で経験していることもあるため、少しは余裕ができるイメージですよね。
~出産~
一人目の出産を経験しているので、なんとなく出産までの流れが分かるようになったので、「心に余裕ができるのでは?」と思っていましたが、私の場合は違ったようです。
嫌なことや失敗したことが、割とトラウマになりやすい性格…というのもあるかと思います。
そして、陣痛が来て「いよいよだ」とさらに、怖いなという感情が大きくなりました。
すると益々痛いように感じ、一人目の時にはほとんど声も出さなかった私が、二人目の時には、大声で叫んでいました。
私の中では、二人目の方が痛みが強かったと思っています。それは、本当にそうだったのか、それとも、「痛い」という思込みが痛みを助長させたのかは分かりませんが…。
出産は、人それぞれ違いますし、痛みの感じ方もそれぞれです。
このケースはあくまでも、私の場合なのでもちろん二人目のほうが痛みを感じなかったという方もいらっしゃいますよ。
~子供が生まれてから~
二人目の出産後に大変な事は、上の子どものお世話と心のケアをすることだと思います。
特に2歳差での出産だと、上の子がちょうどイヤイヤ期と重なってしまう、なんてこともあるのではないでしょうか?
また、赤ちゃん返りが始まったりと、心が不安定になりがちですよね。
そしてもちろんの事ですが、生まれてからも、新生児のお世話に上の子どものお世話は続きます。
赤ちゃんのお世話をしている時に、上の子に「ママ~」と呼ばれることも多いですよね。
上の子どもが熱を出したりすれば、病院に連れて行かなければなりません。

ご夫婦で話し合い、サポートしてもらえる環境を作って、少しでもママが楽になる方法を見つけて欲しいと思います。
二人目の育児は、上の子のケアや外出などが大変だと私は感じました。
それぞれの大変さを私なりに紹介しましたが、もちろん、大変な事ばかりではありませんよ。
一人目、二人目の育児の楽しさの違いとは?

子育てには、つらいことや大変なこともありますが、楽しいこともたくさんありますよね。
では、一人目と二人目の育児では、どんな楽しさの違いがあるのでしょうか?
一人目の育児の楽しさとは
ベビー服やグッズを見ると、とてもワクワクした気持ちになりますよね。
一人目の時は、揃えなければいけないものが多くて大変かもしれませんが、それが楽しみの1つとも言えるのではないでしょうか。
最近では、おしゃれなスタイや、便利なグッズなどもたくさん売っているので、見ているだけでも楽しいですよね。
そして、1番の楽しさはなんといっても、ママと子どもが一対一で関わる時間がたっぷりとあるということ。
初めてのことばかりで、悪戦苦闘することもありますが、じっくりと向き合うことができます。
また、赤ちゃんが寝てくれれば、一緒に身体を休めることができるので、二人目と比べると、ほっと一息つける時間が多いのではないかと感じます。
二人目の育児の楽しさとは
新生児のお世話が2回目なので、おむつ替えや授乳などもスムーズにできるようになります。それによって、心の余裕も生まれてきますよね。
また、上の子どもが一生懸命面倒を見ようとしてくれることもあります。
まだまだ小さいと思っていた上の子どものそんな一面を見ると、成長を感じて嬉しくなります。
上の子がちょっとしたお手伝いをしてくれるだけでも、だいぶ楽になりますし、一人目の時に感じるような、孤独感を味わうことも少なかったように、私は思います。
また、一人目の成長を見ているので、成長過程が分かってきます。
そうすると、次は”こんなことができるようになるかな?”という楽しさも味わうことができますよ。
一人目と、二人目ではそれぞれ違った楽しみがあるものですね。
子育てを経験していくうちに、子どもからも学ぶことがたくさんあると思います。
私は、その学んだことから子育てにも変化が出てきました。
子育てへの思いの変化!?

一人目と二人目では、子育てへの思いの変化も出てくるのではないでしょうか?

私は、保育士ということもあり、たくさんの子ども達をみてきました。
その中で、こんな子どもに育って欲しいな、そのためには、こんな風にしたいな…など、たくさんの理想ができていました。
そして、その理想を叶えようと、1人目の時は、特に必死でした。
おむつ外れが早いと言われている布おむつに挑戦したり…

部屋も常にきれいなように心がけたりと、生まれた直後から、育児本に書いてあるようなことを、片っ端からやろうとしていました。
とにかく、一生懸命で、慎重に、大事に大事に子育てをしてきました。

しかし、二人目が生まれてからは、一人目の時のようにはしませんでした…というよりはできませんでした。
上の子がいるので、下の子ばかりに手をかけられないというのが、1番の理由だと思います。
でも、その他にも理由はありました。
それは、一人目の時にやってきたことを、できなくても大して問題はないなと思ったからです。
良い意味で、肩の力が抜けたのですね。
育児書を見ても、自分の子どものことは載っていませんし、大抵育児書通りにいくことなんてありません。
育児書やネットで調べるより、「自分の子どもをきちんと見よう!」「今まで保育士として働いてきた経験や知識に自信を持とう!」と思うようになりました。

育児に熱心なことが、悪いとは思いません。むしろ、子どものために頑張ることは、母として当然なことですし、素晴らしいことだと思います。
ただ、あまりにも自分の考えや、育児書に頼り過ぎてしまうと、目の前にいる我が子を見失ってしまうこともあるのです。
上手にバランスを取りながら育児を楽しみたいものですよね。
一人目二人目と、それぞれ良い所や大変な所を紹介しましたが、兄弟の年齢差ってどれくらいがいいのか気になりませんか?
一人目と二人目、何歳差がいいの?

二人目を考える時、「上の子と何歳差がいいかな?」と一度は考えるのではないでしょうか?
でもこればっかりは、希望通りに行くかどうかは分からないものですよね。
年の差ごとにどんなメリットがあるのか、考えていきたいと思います。
一人目と二人目が年子の場合
生まれた月にもよりますが、年齢が近いので上の子が使ったものを、片付けずにそのまま使えるというメリットがあります。
それに加え、年子だと赤ちゃん返りが少ないともいわれています。
まだ上の子が赤ちゃんの時にママのお腹が大きくなるため、自然と二人目の存在を受け入れるケースが多いのかもしれませんね。
年子で子育てをすると、長い目で見た時に育児の期間が短いのもメリットかもしれません。
ただ、ほとんど年齢が変わらないので、双子を育てているような大変さを感じることはあるかもしれませんね。
2歳差の場合
先にも述べましたが、2歳と言えばイヤイヤ期真っただ中。
そんな中の子育ては、大変かもしれませんが、下の子が生まれたことによってしっかりした、イヤイヤが減ったという話も耳にしたことがあります。
また、下の子が1歳を過ぎてからであれば兄弟で一緒に遊んでくれるということもあるでしょう。
一緒に遊んでくれると家事をする時間も取れて少し楽になりますよね。
長い目で考えると、中学、高校の入学・卒業が被らないというメリットもありますよ。
3歳差の場合
うちは、まさに3歳差です。上の子が、自分のことなどをある程度一人でできるようになってくるので、少し余裕をもって下の子の面倒が見ることができました。
トイレトレーニングも出産前だったので、ゆっくりと向き合うことができたなと思っています。
上の子は自分が年上なんだという自覚を持ってくれますし、下の子は上の子のやっている勉強にちょっとだけ背伸びをして興味をもったり…なんてことも耳にします。
ただこれから待ち受けている、中学、高校の入学・卒業が被ってしまうのが、大変なところでもありますね。
4歳差以上の場合
4歳以上にもなると、しっかりと下の子の面倒を見てくれる、という場合が多いのではないのでしょうか?
また上の子が、幼稚園や保育園、小学校などに通っている場合が多いと思うので、ママ的にも、下の子とゆっくり向き合える時間が取れるのではないかと思います。
私は三姉妹の真ん中なのですが、4歳ずつ離れています。
私の母は、ひとりひとりの子どもと、4歳までしっかりと関わることができたと、言っていました。
上の子が使っていた服の保管や出し入れ、新たに購入する物が出てくる、などの大変さはあるかもしれませんね。
何歳差が良いとは言い切れません。その家庭によって、生活環境や考え方は違います。
ですから、メリットやデメリットを考えつつご夫婦で話し合って、解決するのが1番いいですね。
一人目の子どもに対して気を付けたいこと

長女、長男というと、なんとなくしっかりしているイメージがありませんか?
上の子だからと、我慢させてしまう事が多かったり、何かとお手伝いを頼んだりと、ママやパパもついつい頼りにしてしまいますよね。
でも、内心では、「もっと甘えたい!」、「もっと構ってほしい!」、「我慢ばっかりで嫌だ!」なんて思っているかもしれません。

- 「お姉ちゃんだから、お兄ちゃんだから」という言葉を使い過ぎない。
→プレッシャーを与えているように感じます。頻繁に言わない様に気をつけましょう。 - 「ちゃんと見ているよ」というメッセージを伝えましょう。
→「自分も見て欲しい!」という気持ちが絶対にあるはず。頑張っている事を、具体的に伝え、努力を認めてあげましょう。 - スキンシップをしよう。
→スキンシップを取ることで、オキシトシンという脳内物質が分泌されます。愛着関係を深めるとともに、ストレス発散にも繋がります。
このようなことに気を付けてあげるといいですね。
二人目の子どもに対して気を付けたいこと

下の子、というと甘えん坊で世渡り上手なイメージがありませんか?
上の子が面倒見てくれたり、親がついつい可愛がり過ぎたり…なんてこともあるかと思います。
では、どんな事に気を付けたらよいのでしょうか?
- 甘やかしすぎない
→ついついやってあげたくなってしまう事もありますが、それでは、子どもの成長の妨げになってしまうこともあります。
子どもができる事は、時間がかかっても見守るようにしましょう。 - 赤ちゃん扱いをしない
→赤ちゃん扱いをして、ママやパパが喜んでいると、子どもはそれに応えようとします。可愛い気持ちが間違った方向に向かない様、1人の子どもとして、しっかりと向き合うようにしましょう。 - 上の子と同様、スキンシップをしよう
→小さい頃からしていると、それが自然な事になるので、続けられやすいですよね。ハグは、大人にとってもストレス発散になるので、いいこと尽くしです。
気を付けたいこともたくさんありますが、兄弟がいるといいなと思うこともありませんか?
兄弟(姉妹)がいていいなと思ったこと

兄弟がいることで、どんなメリットがあるのでしょうか?
遊び相手ができる
ママが手を離せない時、子ども達同士で遊んでいてくれると、助かりますよね。
一人遊びも大切ですが、お友達や兄弟で遊ぶ時間も、とっても大切です。
上の子は、遊びを創り出すのが上手な子が多いです。その遊びを真似することで、下の子も創造力が養われていきますよ。
また、物の貸し借りをしたり、順番を待ったり…と、遊びの中でルールを守ったり、我慢することを覚えていきます。
自然とそのようなことを覚えられるのはとてもいいことですよね。
喧嘩できる相手がいる
ある程度、成長するとそれぞれに意思が出てくるので、その分喧嘩も増えていきます。
「毎日喧嘩が絶えなくて大変!」と思うかもしれませんが、それは、兄弟がいるからこそできることなのです。
喧嘩を通して、相手の気持ちを知ったり、相手との距離の取り方を知ったり、優しさを覚えたり…。
喧嘩も、悪いことばかりではないんです。
”お友達とは、仲良く遊ばせなきゃ”という方も多いと思います。
でも実は喧嘩って、子どもにとっては大切な事なんですよね。
例えば、男の子たちが、殴り合いのけんかをしていると、ついつい止めたくなるかもしれません。
しかしこれは、相手の痛みをしったり、これ以上やってしまったらけがをさせてしまう、というのを学ぶチャンスでもあるのです。
喧嘩した後の方が、仲が良くなったなんてこともありますよね。
この肌と肌とのぶつかり合いをしないと、相手の痛みを知る事できません。だから、カッとなって人を刺してしまうという残酷な事件も起きてしまうのです。
まだ、うまく言葉で伝えられない年齢や、いじめに発展しそうな場合は、大人が介入する必要がありますが、それ以外は、周りの安全を確保しながら、見守ってあげると良いでしょう。
お互いに刺激し合える
年齢が異なる兄弟だと、上の子は、下の子の面倒を見ることが多いのではないでしょうか?
そうすることで、下の子のお手本になろうとしたり、相手を思いやる気持ちが育まれます。
逆に下の子は、上の子に憧れを抱きます。自分ができないことを、やっているお姉ちゃん、お兄ちゃんって凄い!「自分もそうなりたい!」と思うのです。
そうすることで、やってみたいという意欲や、挑戦する心が芽生えます。
我が子を見ていて思う事は、下の子の方が色んな場面において、できることや覚える事が早いなと思います。
そうすると、真似をしたがる次女が一緒にやりたいと、やってくるのです。
最初は、大人と一緒じゃなければできなかったのに、今では、一人で、できるようになりました。
トランプ遊びのお陰で、数字も読めるようになりました。長女が次女の年齢だった頃より、覚えるのが早かったなと思った出来事です。
お互いに刺激し合いながら、成長できるのも、兄弟がいる良さですね。
最後に
一人目も、二人目とそれぞれについて書いてきましたが、一人目二人目に限らず、子どもにはそれぞれ個性があります。
そして、ママやパパとは別人格の人間です。
こどもは、親の思い通りには育ってくれません。
それをきちんと理解した上で、子ども達と関わることを忘れない様にしたいものです。
自分の枠の中に抑えこめようとせず、子ども達の気持ちや考えを認めてあげることが大切ですよね。
それが、親と子どもがいつまでも良好な関係を築ける秘訣なのではないでしょうか。
いつかは、親元から離れていく我が子。厳しい社会の中で、強く生きられる力、心を育てていきたいものですね。
突然ですが
今、おしゃれできていますか?
私は子供が生まれてからというもの、まったくおしゃれができなくなりました。
子育てが忙しく毎日、同じ洋服を着て出社をしていました。そんなある日、職場の若い女の子に
「毎日同じ洋服で楽そうですね、でも私はそこまで女を捨てられません」
なんて言われる始末。子育てが忙しいからおしゃれなんて無理…そう思っていました。
しかし!
ものすごい簡単におしゃれができてしまう方法があったんです!
この方法ならお金も節約できるし、おしゃれも楽しめるし一石二鳥、いやそれ以上です。私はこの方法に出会ったおかげで毎日おしゃれを楽しんでいます。
職場でも「おしゃれですね!」って言われて最高に嬉しいです。