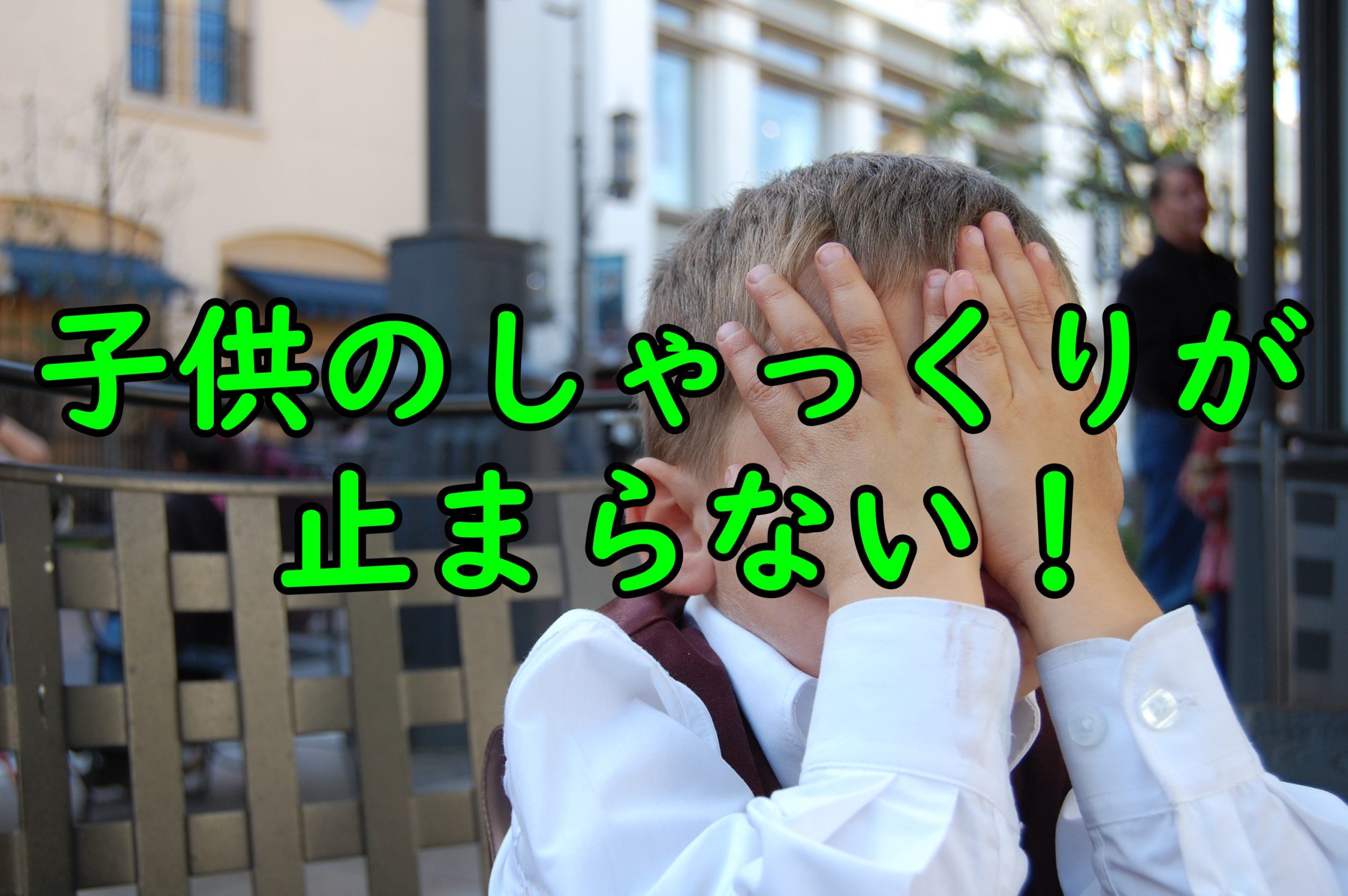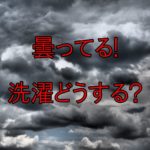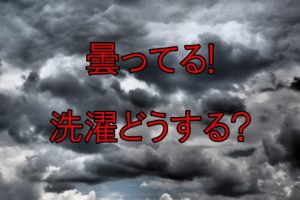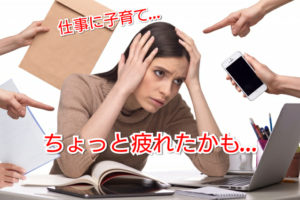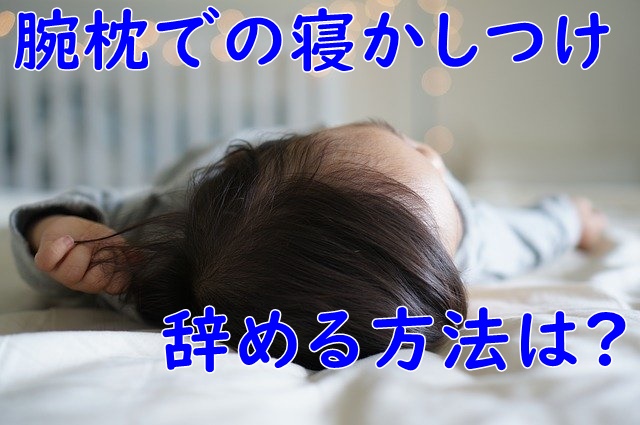子供、特に赤ちゃんって、よくしゃっくりをしますよね。
しゃっくりは生理現象とはいえ、回数や程度がひどくなると、心配になるママやパパも多いのではないでしょうか。
小さな赤ちゃんが長い間しゃっくりをしていると、きつそうに思えて「何とか止めてあげたい!」と思いますよね。
たかがしゃっくり、されどしゃっくり。
そのままにしておいて大丈夫?病院に連れて行くのはどんな時?など、意外と頭を悩ませるものです。
今回は、我が子のしゃっくりに落ち着いて対応できるように、しゃっくりの原因と対処法について見ていきましょう。
目次
しゃっくりの原因は意外なところにあった⁈

そもそもしゃっくりはなぜ起こるのでしょうか?どんな仕組みなのでしょう?
|
しゃっくりが出る仕組み 呼吸を補助する筋肉と横隔膜が急に収縮し、けいれんすることで現れる症状 |
新生児の赤ちゃんは神経系と筋肉組織が未熟なため、よくしゃっくりをして吐いてしまうこともあります。
しかし、成長とともにしゃっくりが出る回数は徐々に減っていくので、基本的に心配はありません。
されどしゃっくり!起こる原因って考えたことありますか?
私は長らく、しゃっくりに原因があるとは考えたことがなく、いきなり始まるから防ぎようがない、やっかいなものと思っていました。
しかし息子の頻繁なしゃっくりが心配でいろいろと調べてみると、しゃっくりが始まる原因にはいつくかのパターンがあることが分かりました。
しゃっくりが起こった時、当てはまるものはないか確認してみてください。
赤ちゃんの体が急に冷えた!
気温が下がってくる寒い時期に、よくしゃっくりが出ると言われます。これは冷たい空気が肺に入ることで、横隔膜を刺激するからなんだとか。
他にも急な温度の低下が起こるシチュエーションは意外と多いです。
- 室内から外に出た時
- 突然服を脱がせた時
- お風呂から上がった後
- おむつが濡れている時
- 冷たい牛乳を飲んだり、冷たい食べ物を食べた時

あんまりびっくりさせないで!
赤ちゃんが驚いた時、しゃっくりが始まることがあります。
- 急に赤ちゃんの姿勢を変える
- ドアをバタンと閉める
- 何かが飛び出した時
このような出来事で、赤ちゃんのしゃっくりって簡単に始まってしまいませんか?
驚いた時にしゃっくりが始まるのは、呼吸の動きがいつもより速くなり、横隔膜が刺激されるからなんですよ。
母乳やミルクの飲み過ぎ?早食い?
胃の容量が小さい赤ちゃんが、飲める量を超えて母乳やミルクを飲み過ぎることもしゃっくりの原因になります。
また急いで飲んだり食べたりすると、飲み込む時に空気が一緒に入り、胃が膨張して横隔膜を刺激する恐れがあります。
母乳やミルクの量を適切に調節し、ゆっくり飲む・食べるを意識するといいですね。

意外と知られていない?!心理的ストレス
不安や焦燥感のある状況、またはストレスなど心理的な原因でしゃっくりをすることもあります。
子供の普段の様子を注意深く観察し、何かストレスになってはいないか、気をつけて見てあげてください。
見て!というサインかもしれませんね!
試す価値あり!しゃっくりを止める方法10選

自然な現象だから気長に見守ろう、と言われても、しゃっくりって出る日は何度も出るし、「ひっく、ひっく」という音を聞いていると、どうしても心配になってしまいますよね。
ここからは、息子のしゃっくりを止めるのに効いた方法や、ママ友や母から教わったしゃっくりを止める方法をご紹介します。
身体が冷えちゃった?
【①まずはおむつを確認】
急にしゃっくりが始まったら、私はまずおむつが濡れていないかを確認しました。
おむつが濡れていると、こちらが思っているより体が冷えるようです。
おむつを替えた後にピタッと止まったりするので、まず確認してみてくださいね。
その際、おむつを変える場所が寒いところだと、逆効果になってしまう可能性も!
【②寒さは大敵!体を温めてあげよう】
急な温度の低下でしゃっくりが起こったようであれば、帽子をかぶせてあげたり、ブランケットなどで暖かくくるんであげましょう。
頭は私たちの体から体温が抜けていく場所の一つです。
そのため頭を温めると、しゃっくりを止めるのにも効果があります。

とにかく冷えた体を温めてあげるといいみたいです。
その他の体を温める方法としては、暖かい布団に寝かせる、ぬるま湯を飲ませるなどもありますよ。
ゆっくり~ちょっとずつ~そっと~
【③授乳や食事はゆっくり】
授乳や食事の時によくしゃっくりが出るとお悩みの場合は、普段飲む量・食べる量より量を少なくしたり、数回に分けて与えるなどしてみてください。
どうしてもゴクゴク飲んでしまう子、パクパク口に入れてしまうような子は、途中で休みながらゆっくり食べるように手助けしてあげましょう。
ゆっくり食べるということは、体にいいことばかりなので、意識していきたいですね!
【④そっと抱いてあげて安心させてあげる】
あるママ友は、子供をそっと抱いてなだめてあげると、しゃっくりが止まるようだと話してくれました。

で述べたようにしゃっくりは心理的ストレスが原因の場合もあるため、子供が安心感を感じるようにしてあげるのは効果があるのかもしれませんね。
心苦しいけど…致し方ない!
【⑤少し泣かせる】
反対に、しゃっくりが出たら赤ちゃんをちょっと泣かせる、というママもいます。泣くことによっても横隔膜が刺激を受け、しゃっくりが止まるようです。
足の裏を少しくすぐったり、赤ちゃんの嫌がる行動をしてみるそうです。
泣かせるのは少し心苦しいですが、長時間続くしゃっくりが止まるのなら、試してみてもいいかもしれません。

【⑥ティッシュを用意!くしゃみをさせる】
古典的な方法ですが、ティッシュでこよりを作って、赤ちゃんの鼻にこっそり入れてみるという方法もあります。
意外と、くしゃみした後、しゃっくりが止まっていることって多いですよ。
大人でも、試したことがない方は一度試してみるのもありです!むずむずしますけど(笑)
刺激を与えてあげる!届け!
【⑦耳周りの神経を刺激】
耳の近くには様々な神経が分布しており、この中には横隔膜とつながっている神経もあります。
そのため、耳の周辺を優しく触ったり、耳を少しふさいだり、耳の穴に指を入れて少し押したりすると横隔膜に刺激が伝わり、しゃっくりが止まることがありますよ。
【⑧砂糖水で脳を刺激!】
濃度の薄い砂糖水をティースプーンひとさじ程度飲ませると、脳が新しい刺激に反応してしゃっくりが止まる可能性があります。
ある程度成長した子供なら、砂糖水の代わりに飴をなめさせるのも一つの方法です。
吸って!止めて!はいて~
【⑨息を止めて!止めて!】
言葉が分かる子供なら、息を止める方法を教えてあげてもいいかもしれません。
息をできる限りたくさん吸って止め、大きく吐きます。
息を止めている間、血液中の二酸化炭素が増加し、吐く時に脳がそれを外に出すことに集中するため、しゃっくりが止まる仕組みなんですよ。
【⑩げっぷをさせる】
授乳の際、空気を飲み込んでしまってお腹が膨れ、それがしゃっくりにつながっていることがあります。
げっぷで胃の中の空気を抜いてあげることで、しゃっくりが止まることもあります。
赤ちゃんの体を、抱いている人の体にくっつくように垂直にして、背中をトントン叩いてあげましょう。
赤ちゃんを「うつぶせ寝」させて止めようとするのは、窒息やSIDS(乳児突然死症候群)の危険があるので絶対にしてはいけません!
しゃっくりを伴う病気の可能性

しゃっくりは、まれに何らかの病気が原因で起こっていることがあります。
24時間以上1回も止まらずにずっとしゃっくりをし続けるような場合は、念のためかかりつけ医を受診してください。
しゃっくりに加えて以下の症状が続いている場合も専門医の診療を受けましょう。
|
さいごに
親としては、しゃっくりしている我が子がきつそうに思えて、心配になりますよね。
しゃっくりが出たら、まずは落ち着いて今回ご紹介した原因ではないか確認してみてください。
そしてママとお子さんが試しやすい対処法を実践してみてくださいね。
どうしても心配な時は、ためらわずかかりつけ医に相談しましょう。
突然ですが
今、おしゃれできていますか?
私は子供が生まれてからというもの、まったくおしゃれができなくなりました。
子育てが忙しく毎日、同じ洋服を着て出社をしていました。そんなある日、職場の若い女の子に
「毎日同じ洋服で楽そうですね、でも私はそこまで女を捨てられません」
なんて言われる始末。子育てが忙しいからおしゃれなんて無理…そう思っていました。
しかし!
ものすごい簡単におしゃれができてしまう方法があったんです!
この方法ならお金も節約できるし、おしゃれも楽しめるし一石二鳥、いやそれ以上です。私はこの方法に出会ったおかげで毎日おしゃれを楽しんでいます。
職場でも「おしゃれですね!」って言われて最高に嬉しいです。