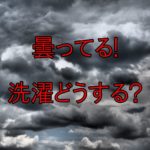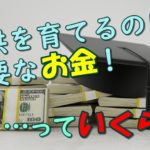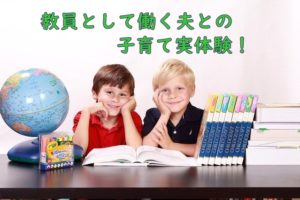「ご家庭では、教育方針についてどのようにお考えですか?」
こんな質問をされたとき、皆さんは答えることができますか?
答えが思い浮かんだ方。
その答えで本当に合っていますか?
なぜ、自分の子どもの教育方針なのに自信がなくなってしまうのでしょうか。
教育方針をはっきりさせておくと子供を叱りすぎることがなくなり、子育てが少し楽になります。
私が子育てしていた中で思った教育方針がわかる方法をご紹介しましょう!
これからお受験を控えているという方も、子供のしつけで悩んでいる方も、この記事をご覧になってみてください。
目次
教育方針は家庭のルールからわかる

教育方針とは‥
実は、紐解いていくととてもシンプルで、難しく考える必要が無いものなのです。

ですが、そもそも教育方針というのは家庭のルールで大事にしていることなのです。
あなたの家庭内でのルールについて考えてみましょう。
例えば、
- 出したオモチャを片付ける
- 自分が食べた食器は下げる
- 朝は自分で起きられるようになる
この3つのルールは、我が家で実践しているルールなのですが、どの項目にも共通するのは「自立心を育てる」ということ。
家庭内のルールで共通している事項が教育方針なのです。
こんな子に育って欲しい‥
という親の想いが家庭内のルールには現れますよね。
そのルールから教育方針がわかります。

あなたのお家の教育方針についても、ルールから紐解いて考えてみましょう。
家庭内のルール‥?そういえばきちんと決まったルールがないなぁ‥
と感じている方は、お子さんにどんな子に育ってほしいと考えていますか?
将来を具体的に想像してみましょう。
その想像した将来の子供に必要な能力が身につくようなルールを作ってみませんか?
まずは、あなたがざっくりとしたルールを決めて「こんなルール作ってみよう!」と子供に提案してみましょう。
ルールを作って、子どもがそのルールを守ることができたら褒める!
また新たなルールを作って、守ることができれば褒める!
その繰り返しをすることで、子供が成長していきますよね。
そうやってルールを増やしていく中で教育方針が自ずと見えてきます。
ちなみに‥
私の友人の家庭(子供は4歳)では、主なルールはないそうなのです。
ですが、これをしたら褒める!というポイントがあり、そのポイントを教えてもらいました。
コチラです↓
- ご飯を残さない
- わからない事があれば聞く
この2つのポイントには、一見統一性がないように思われます。
ですが、自分で物事をやり遂げる力を身につけることができるでしょう。
友人自身も、この統一性には気付いていないかも知れませんが、子供への願いはたっぷり詰まっているように感じます。
教育方針とは、このようなもので良いんです。
難しく考えずに、子供には何を大切にしてもらいたいかということを考えてみましょうね。
- 教育方針を難しく考える必要はない
- 家庭のルールに共通している事が教育方針
- ルールがなければ、子供と作ってみよう!
続いての項目では、教育方針が定まっていると良いことについてをご紹介します。
教育方針が定まっていればブレることがない

親が子供を育てるのは勿論ですが、子どもを保育園や幼稚園に通わせるようになると、子ども同士の社会が始まります。
そこでは気の合わない友達とも付き合わなければいけないし、自分中心に過ごしてはいけない場面も多いでしょう。
通う前は、気の合わない子とは親がトラブルが起きないように計らえばよかったのですが、保育園や幼稚園へ通うようになるとそうもいきません。
子供が、集団生活を始めた時、子供社会の問題が起きるのです。
そこで、教育方針を大いに活用することができます。
我が家は、子どもを保育園へ通わせていました。
保育園へ入園した頃は、お迎え時に、先生から「今日は、お友達と上手に意思の疎通が取れなかったようです」とトラブルが起きたことを教えてもらうことがありました。
我が家の教育方針は【自立心を育てること】なので、問題が起きた時、細かく口出しすることはありません。
帰り道に、「今日、保育園楽しかった?」や「今日の保育園で思ったこと教えてほしいな」などと、直接的にならないように計らいながら、子供の言葉で話を聞きました。
子供はよく覚えていないのか、先生から聞いた問題を自ら話さないのです‥
親の私には話さなくても、子供自身でなにか感じていることはあるだろうとしばらくは見守るに徹しました。
すると「〇〇ちゃんゴメンって言ってた〜!」と報告を受けたのです。
子供はなにについて謝られたのかわかっているのか?と疑問がありましたが、とにかく私からすれば、自分で問題を解決できていることがすっごく嬉しかったのです(笑)
意思の疎通が上手くいかなかったお友達と話すことができている!と。
その喜びを抑え、親としてさらに自立心を伸ばせるような声かけを意識します。
「そっか。〇〇ちゃん偉いね、ごめんて言えたんだね」等、向こうの子を褒め「なんで、〇〇ちゃんが偉かったんだろう?」と、子供に聞いてみました。
答えは「ごめんって言えたから偉いんだ‥!」なんて閃いたように言うけれど、ほぼ私の言っていることのパクリです(笑)
ですが、「そうだね〜!◯◯もちゃんと考えて偉いね〜!!!」と考えられたことや答えられたことに対して、自分の子供も褒めました。
結果、私の子供はトラブルが起きた時に自分で解決する高い能力が身につきました。
コミュニケーションがうまく取れるようにもなり、毎日の保育園が楽しそうでした!
子どもからしてみると保育園は、自分の社会ですから、自分で解決できるところは子どもに解決させるようにしないと!と、私は日頃から思っています。
人間関係の問題は、大人になれば自分で解決しないといけないもの。

自立心とは、「人に頼らず自分でどうにかしようとする心」ですから、教育方針が定まっていなければ、トラブルが起きた時、私が介入しまくまっていたかもしれません(笑)
例えば、人に優しくできることを教育方針として定めていたなら、「友達にはおもちゃを貸してあげようね〜」と声かけをしていたはずです。
教育方針はみんな同じでなくて、家庭それぞれで良いのです。
不安になる必要はありませんよ。
家庭の教育方針をハッキリさせておき、その教育方針に沿って子供に接することができれば良いですね。
教育方針が定まったからといって、子供がその通りに育つよう押し付けすぎると、子供が辛くなってしまうことがあります。
できないことができるようになるまで、辛抱強く、長い目で見てあげましょう。
子供の成長に合わせて、その都度考えて行くことがいい方法だと言えるでしょう。
教育方針は子供の成長に合わせて変えたい

例えば子供が3歳の時に教育方針を、「社会で一人で生きていけるようになること」と親が決めたとします。
この教育方針ならば、手伝いという名の仕事を子供に与えるでしょう。
その手伝いが3歳の時も5歳の時も同じではいけませんよね。
3歳の時に自分の食べた食器はキッチンに下げる手伝いをしていたならば、5歳になれば、洗い物に挑戦することを提案すれば、子供がステップアップできます。
実は、ここが親が怠けてしまうところなんです。
次に挑戦してもらいたいことを提案しなければ、子供も自分に満足して、出来たことができなくなってしまうことがあります。

程よく子供を頼る時間を増やして行くのが良いでしょう。
習慣づけも、勿論大切ですが、子供が成長できるように数ヶ月ごとに小さい目標をたてるのがオススメです。
できるようになっている‥!とわかれば、子供もやる気をなくすことはありません。

大人もそうなのでね(笑)
ここからは私のお話です。
子供が生きてくれているだけで幸せ‥!と本気で思っていました。
それは今も変わり無いのですが、やはりしつけは大事だと感じています(笑)
実は、子供がわがまま放題になり、夫と話した結果、「自立心を育てる」という教育方針が定まったのです。
息子が3歳の頃、ご飯を全く食べませんでした。
イヤイヤ期という言葉があり、まだ続いているのかな?くらいに思っていたのですが、息子は「お菓子がほしい」と泣き喚くことが多々ありました。
私はご飯を食べてくれるだけで充分‥!と考えていて、無理に食べさせることもしませんでした。
そこが私の怠けポイントです(笑)
こんなんじゃ自立心なんて育たないよな‥と思い始めた頃‥
さすがに夫に「◯◯やばいよ、わがまま言うことも多いし‥少し考えよう」と提案され、私は、言葉のチョイスや表情・行動を変えることを特に意識しました。
「ご飯食べなくちゃおっきくなれないよ〜?」と悲しそうな顔をして、声をかけたり、「◯◯ご飯の前にお菓子を食べるのはダメなことだよ!」と真顔で強めに伝えるようにしました。
すると、子供も私の表情や態度を読み取ってか、「ごはんいっぱい食べられるよ〜」と言って、ご飯前に親戚にお菓子をもらってもご飯を食べた後でなければ食べないようになりました。
イヤイヤ期だからといって、あの頃のままの育児を続けていたら‥と考えると、本当に怖いです(笑)
今では「からっぽっぽ〜」とお皿が空っぽになったことを毎食教えてくれます。
ご飯を食べるだけで充分と思わず、年齢に合った声かけや教育が大切なのだと感じた瞬間です。
子供もご飯を全部食べることができると嬉しそうです。
怒らない子育てが主流になりつつある今、家庭内で教育方針を定め、年齢に合わせて子供をしつけることはとても大切だと感じています。
親が、子供の能力を見定めることが肝となってきますね。
教育方針に沿って育てるためには声かけが重要

今では、子供への声かけを最重要視している私ですが、言葉一つで子供のやる気が変わります。
理解度も変わります。
教育方針を押し付けすぎると、子供への負担が大きくなってしまうことがあります。
ですが、親の声かけで、子供が押し付けられていると感じないようにすることもできます。
それは、行動への説明をしておくことです。
子供に話してもわからないんじゃないの?と考えてしまいますが、意外と3歳でも5歳でも理解はします。
それ以上大きければ、もっと理解してくれます。
注意点としては、子供が理解できるような言葉をチョイスすること。
声かけの実際の例をご紹介しましょう。
くつをならべると玄関がキレイになって帰ってきたパパがきもちいいでしょう?
次に来た人の邪魔になることがないよ
怒らず、真顔で伝えるようにします。
くつはなぜ並べることがどんな意味を持つのか、行動の説明をします。
今からでかけるからおもちゃを直そうか
出したまま出かけると、帰ってきた時気持ち悪いよ
その場面に合った声かけをしましょう。
我が家では、気持ち良いや気持ち悪いと言う言葉をよく使っています。
子供たちにも気持ちが良いという感情を覚えてもらいたいからです。
片付けや、靴並べが意味のないものになってしまうと悲しいですよね。
一度で覚えてくれることはまずありませんが、行動への説明をしておけば、必ずできるようになります。
子供を信じましょう。
教育方針の実際の例

ここまでは、教育方針を緩く考える方法や、私の体験談を踏まえたお話をしましたが、いざ、人に話せるような教育方針とは、どんなものなのでしょうか。
例を考えてみました。
私どもは子供に、自立心を身につけ、まっすぐに育ってほしいと日頃より考えております。
自立心を育てる上で大切にしていることは、自分でできることはするということです。
夜に目覚まし時計をセットし、朝は自分で起きます。食べた食器は自分でさげます。このような手伝いをすることにより、毎日の自分の仕事を増やしています。
人に甘え過ぎないこと、迷惑をかけないことに重きをおいて躾をしております。
最近では、自分でどうにかしなければと考えられるようになり、友達とのトラブルも自分で解決できるようになりました。
物の貸し借りがスムーズに行えたり、大人数で遊ぶことができます。
コツとしては、
- 日頃から大切にしていること
- 具体例
- 子供ができること
このような流れで伝えるとキレイにまとまります。
受験を控えている方はぜひ、参考にしてみてくださいね。
まとめ
我が家では、我が子が成人して社会に出た時に一人でも生きていけるように育てたいと思っています。
私たち親は、いつまでも子どもと一緒に口煩くしていられません。
私の考える教育方針は「子どもが1人でも社会で生きていけるよう、どう育てるか」なのかなと思います。
教育方針だけが明確に見えていても、子供がその通りに育つわけではありません。
長い目をかけて、少しずつ教えていくことが大切でしょう。
親の思い通りにしたくて子どもにイライラしてしまうことがないように。
教育方針を押し付けすぎると、親の私たちは子どもの為だと思っているのに、子どもは萎縮してしまう‥なんという悪循環。
子供の得意不得意を見分け、それに沿って教育方針を考えてみましょうね。
突然ですが
今、おしゃれできていますか?
私は子供が生まれてからというもの、まったくおしゃれができなくなりました。
子育てが忙しく毎日、同じ洋服を着て出社をしていました。そんなある日、職場の若い女の子に
「毎日同じ洋服で楽そうですね、でも私はそこまで女を捨てられません」
なんて言われる始末。子育てが忙しいからおしゃれなんて無理…そう思っていました。
しかし!
ものすごい簡単におしゃれができてしまう方法があったんです!
この方法ならお金も節約できるし、おしゃれも楽しめるし一石二鳥、いやそれ以上です。私はこの方法に出会ったおかげで毎日おしゃれを楽しんでいます。
職場でも「おしゃれですね!」って言われて最高に嬉しいです。